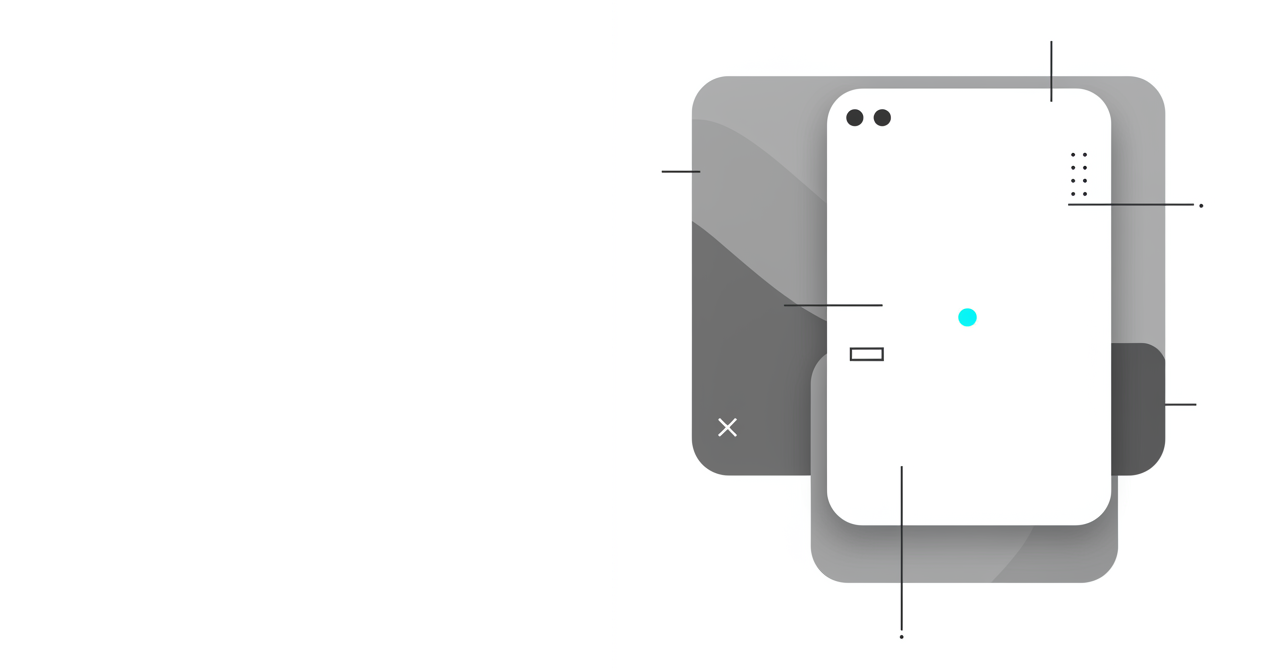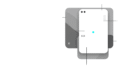はじめに
デザインを考える時、多くの人は「見た目」や「操作性」を思い浮かべると思います。
でも本当に欠かせないスキルは「倫理」だと感じています。
なぜなら、デザインはそれに触れる多くの人々に影響を与えるからです。
ボタン・色使いだけでなく、言葉づかいで人の選択や行動を変えてしまいます。
その責任を意識せず、「使いやすければいい」で進めると、気づかないうちに誰かを傷つけたり、排除したりしてしまいます。
1. 支配的な文化
支配的な文化と聞くと、独裁国家をイメージしてしまうかもしれません。でも企業文化もそれに該当します。
会社が持つ常識や前提は、無意識のうちにプロダクトにも反映されます。
例えば、残業は当たり前という文化を持つ企業が作るサービスには、その空気が滲み込むことがあります。また、恐怖で支配したり、社員たちによる無視といった行動も、支配的な文化に該当します。
デザイナーはそうした支配的な文化に流されないような視点を持つ必要があります。
2. 疎外された人々
障害を持つ人、病気を持つ人、多様な気質や特性を持つ人、テクノロジーにアクセスできない人たち。
そうした人たちを例外として切り捨てるデザインは、社会全体の不公平さを強化してしまいます。
デザインの目的は、大多数に合わせることではなく、できるだけ多くの人に届けることだと思います。
3. エッジケース
「そんなユーザーはほとんどいないから切り捨てていい」
プロダクト開発でよく聞くフレーズです。
でも、実際はそのほとんどいない人たちが確実に存在しています。
彼らを置き去りにするかどうかで、デザインの価値は変わります。
4. インクルーシブデザイン
インクルーシブデザインは、誰もが参加できるようにするデザインの考え方。
日本では、年齢や性別を理由にした差別もまだ多く見られます。
ここで大切なのは、最初から多様性を前提にすることです。
後からアクセシビリティを追加するのではなく、最初の段階で誰が除外されるのかを考えることが重要です。
5. 説明責任
デザインには、なぜそうしたのかを説明する責任があります。
ユーザーにとって不利益になる仕組みを隠したり、都合の悪い情報を小さく表示するのは、倫理的に誠実じゃありません。
実際、デザインツールを提供する大手企業がこのアンチパターンを採用していました。
6. 倫理的デザイン
- 効果的なコミュニケーションを確保すること
- 公平性を重視すること
- 誰かを置き去りにしないこと
美しいビジュアルやスムーズな操作ももちろん大事なのですが、その土台に倫理がなければ、どんなに見た目が美しくても、それは人を幸せにはしません。
さいごに
デザインはプログラミングと同じく、小さな積み重ねでできています。
だからこそ、その一つ一つに、外界への影響を意識することが重要だと思います。
「これは便利か?」だけではなく、「これは誰を幸せにするのか?」
そう自分に問いながら、デザイン力を上げていきたいです。