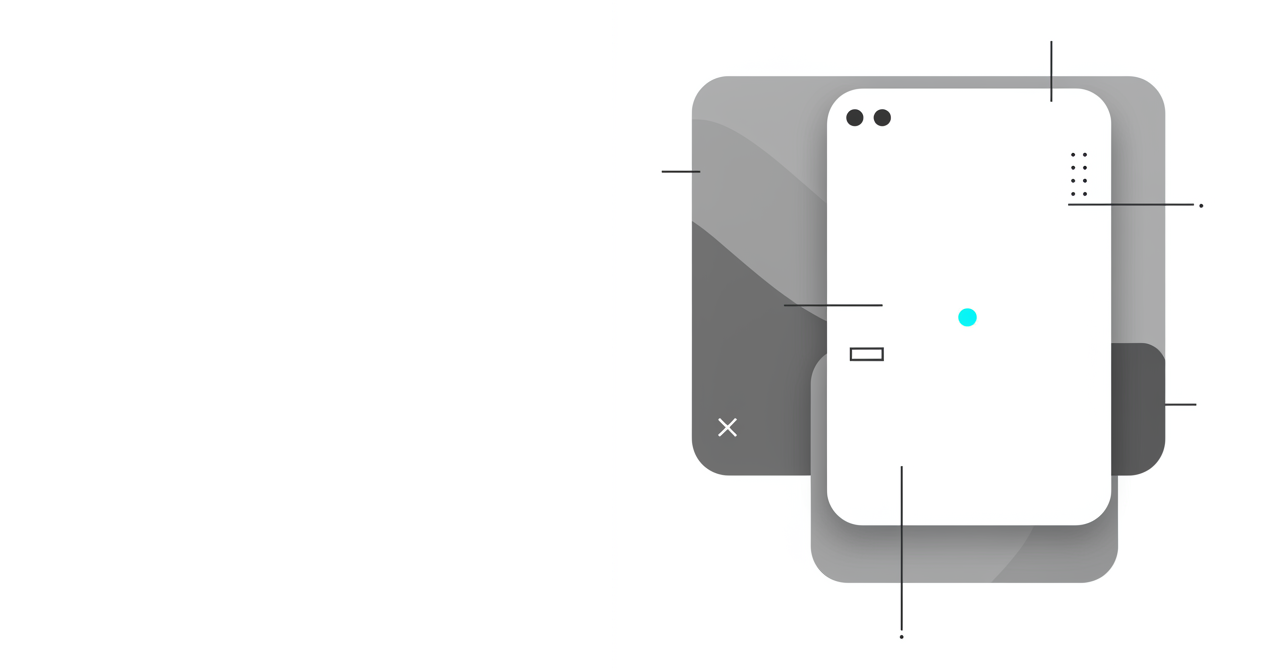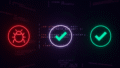はじめに
久しぶりにデジタル庁が公開している「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を読み直しました。
Webアプリを開発するうえでアクセシビリティを考慮することは、結果的に誰にとっても優しいアプリにつながります。大切なのは「対応すること」自体よりも、「なぜそれが必要なのか?」という背景を理解することだと考えています。
ガイドブックの「ウェブアクセシビリティの基礎編」には、その背景や考え方がまとまっていて、とても参考になります。今回はその内容を整理しながら、自分なりのメモを残しておきます。
※詳細はガイドブックをご参照ください。

ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック|デジタル庁
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを一気呵成に作り上げることを目指します。
ウェブアクセシビリティとは
アクセシビリティとは?
- Accessibility = Access + Ability (アクセスする + 〜できること)
ウェブアクセシビリティが確保できている状態
- 目が見えなくても情報が伝わる・操作できること
- キーボードだけで操作できること
- 一部の色が区別できなくても情報が欠けないこと
- 音声コンテンツや動画コンテンツでは、音声が聞こえなくても何を話しているのかがわかること
ウェブアクセシビリティの恩恵を受ける日本人
- 日本だけでも428万人以上
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 視覚と聴覚の両方に障害(盲ろう)
- 上肢障害
- 発達障害、学習障害、知的障害
- 色覚特性
- 高齢者
- 一時的な障害(眼鏡を忘れた、怪我をしてマウスを使えない)
よくある誤解
- 文字サイズ拡大ボタン、カラーテーマ変更設定は、アクセシビリティ確保ではない
- ウェブアクセシビリティの自動チェックツールを使い、ページやサイト全体をチェックして改修することだけがアクセシビリティ向上の方法であると勘違い
ウェブアクセシビリティは「人がチェックする必要がある」
アクセシビリティとユーザビリティ
- ユーザビリティ
- 「特定のユーザーが特定の利用状況において、システム、製品またはサービスを利用する際に、効果、効率、および満足を伴って特定の目標を達成する度合い」
- 少し言い換えると
「特定のユーザーが特定の状況で特定の目的を達成するための、有効性、効率性、満足度のこと。」
- アクセシビリティ
- 「障害者・高齢者を含む利用者のアクセスしやすさ」
- 「あらゆる人のユーザビリティ」
- UXハニカム
- Useful:役にたつ
- Desirable:好ましい
- Accessible:アクセスしやすい
- Credible:信頼できる
- Findable:見つけやすい
- Usable:使いやすい
- Valuable:価値がある
ウェブアクセシビリティのガイドラインと規格
WCAG
- WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
- 現在は「2.2」
- WCAG2.0は、「知覚可能」「操作可能」「理解可能」「堅牢」の4つの原則と12のガイドラインから構成される。さらに細分化した61の達成基準がある。
JIS X 8341-3
- 正式名称「高齢者・障害者等配慮設計指針 – 情報通信における機器、ソフトウェアおよびサービス – 第3部:ウェブコンテンツ」
- ウェブサイトやシステムのアクセシビリティに関するJIS規格
他によく参照される基準等の考え方
- みんなの公共サイト運用ガイドライン
- 情報アクセシビリティ自己評価様式
JIS規格に対応したウェブサイトを作る
JIS X 8341-3:2016 対応度
- 準拠
- 試験を行って達成基準全てを満たす
- 一部準拠
- 今後の対応方針を記載
- 配慮
- 試験の実施と公開の有無は問わない
ウェブアクセシビリティ方針を決める
- 対象となる範囲を決める
- ドメイン、サブドメイン単位
- 目標とする適合レベルを決める
- 原則AA
ウェブアクセシビリティの試験を行う
- 達成基準
- WAIC「実装チェックリスト」
さいごに
「アクセシビリティ対応」と聞くと、特別なものや大変な作業のように感じるかもしれません。ですが、実際にはユーザビリティの延長線上にあり、すべての人にとって快適な体験を提供するための取り組みです。
自分自身の制作プロセスにも少しずつ取り入れていきたいと思います。